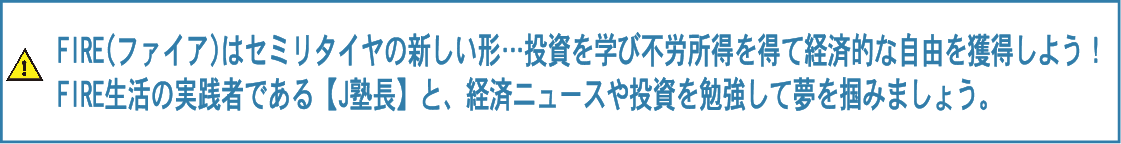【FIRE後の生活】国民健康保険料を甘く見てはいけない

日本は国民皆保険制度を導入しており、日本に永住する人は公的健康保険に加入しなくてはなりません。
塾長はFIREを実現させるまでは、地方の観光地で小さな法人を経営していました。
いわゆる脱サラであり、会社を立ち上げる前は大きな企業の技術職として働いており、保険は健康保険(組合保険)に加入していました。
サラリーマンと自営では何がちがうの?
一般的なサラリーマンは健康保険(協会けんぽ)、大企業などは健康保険組合、また公務員などは共済保険に加入しています。
そしてそのほかの自営業者やフリーターなど組織に属さない人は全て、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
本日のブログはFIRE(ファイア)を開始することで起きる、国民健康保険の問題について解説します。
民間の保険については「FIRE生活で必要なのは医療保険とガン保険…おすすめは?」などをご覧ください。
国民健康保険の請求に驚いた
J塾長が会社を辞めて独立したのは11月です。
会社の立ち上げもあり忙しく毎日を過ごしていたのですが、売上は予想よりも少なく赤字状態でした。
まあ予想通りの赤字が続きましたが、設備投資による消費税の還付が期待できたことから何とか問題なく年を超せたのです。
そして企業2年目となり売上も少しづつ上がってきたところに「ヤツ」が現れました。
えーっ
ヤツってなに?
それは「国民健康保険の納付書」です。
中をみるとなんと家族全員で60万円を超えています。
赤字なのに60万円は辛いね。
当時は赤字であるにも関わらず融資の返済が毎月50万円もあり、現実として60万円以上もの国民健康保険を支払うことはできません。
市役所で相談したしたのですが、国民健康保険はあくまで「税金」であり、前年の所得で計算されることから、現時点でお金がなくても支払ってもらうと相手にされませんでした。
それは厳しいね。
国民健康保険の支払いを考慮しないで資金を使ったJ塾長が悪かったのですが、なんとか工面して期日ギリギリで支払った記憶がありますね。(泣)
このようにサラリーマンから独立することで、国民健康保険の支払いに窮することは珍しくありません。
でもそれはFIRE(ファイア)もおなじことです。
FIRE(ファイア)においても国民健康保険が理由で、生活に支障がでる場合はあります。
国民健康保険は翌年の負担に注意
国民健康保険は「所得割」、「均等割」、「平等割」の合計で算出されます。
所得割とは前年の総所得に対して33万円の控除を差し引いた金額で計算されます。
また均等割りは国民健康保険の加入者数で均等に加算され、平等割は加入世帯で平等で同じ金額を負担する保険料です。
国民健康保険でとくに注意しなくてはならないのは所得割であり、前年の所得が多いほど国民健康保険税額も大きくなります。
FIRE(ファイア)を始めて収入が少なくなっても、翌年の国民健康保険は多く支払う必要があるのか。
所得税につてはサラリーマンを辞めるまでは源泉徴収されているので、確定申告するだけで大きな支払いは必要ありません。
しかし国民健康保険は翌年にまとめて請求されるので、あらかじめお金を用意しする必要があります。
サラリーマン時代の収入が多い人は50万円~70万円程度必要なので余裕を持った準備が必要ですね。
FIRE後の国民健康保険を少なくすす方法①
FIRE(ファイア)で国民健康保険を少なくする方法として有効なのは、最低限のアルバイトの活用です。
現在国の方針で1ヵ月に88,000円程度の収入があれば、会社の健康保険に加入する義務が生じています。
たとえば時給1,000円で6時間はたらくと6,000円、月に15日働くことで90,000円の収入です。
この状態になると国民健康保険ではなく、健康保険(協会けんぽ)の加入義務がうまれるので、費用を抑えて健康保険に加入できます。
また家族を扶養することで、国民健康保険よりも安く健康保険に加入できます。
そうか
会社の健康保険に加入すれば高い国民健康保険を支払う必要がないんだね。
とりあえず最低限のアルバイトでもよいので、月88,000円程度働いて健康保険に加入した方がよいと思います。
また翌年の年収はアルバイト収入だけになるので、その時点で国民健康保険に移行しても保険料は高額にはなりません。
FIRE(ファイア)後の数年は、アルバイトで健康保険に加入するのもおすすめです。
FIRE後の国民健康保険を少なくすす方法②
FIRE(ファイア)を始めるために会社を退職しても、手続きをおこなうことで会社の健康保険の任意継続が可能です。
任意継続の手続きは会社を退職して20日間以内に行う必要があり、2年間継続してサラリーマン時代と同じ健康保険が利用できる制度です。
ただし、サラリーマン時代の健康保険料は会社が一部負担していましたが、任意継続では保険料の全額を負担しなくてはなりません。
任意継続の場合は全額自己負担になるんだね。
全額自己負担になっても家族が多いと、国民健康保険よりも安くなる可能性が高くなります。
FIREで会社を辞める場合には、会社の担当部署に相談して選択することをおすすめします。
FIRE(ファイア)を始める生活費だけでなく、税金や健康保険などの支払いも自分でおこなわなくてはなりません。
負担を少しでも減らす努力も必要ですね。