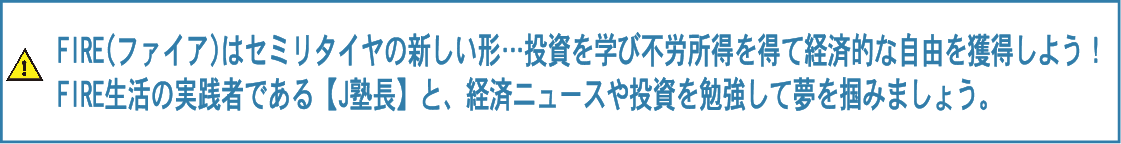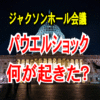FRB議長が利上げ継続を明言…利上げ継続で株価上昇のなぜ?

2022年9月12日の日本株式市場は大幅な上昇からスタートしています。
10時現在の日経平均は346.45円高の28,561円になっているよ。
米国の利上げの問題から一時的に軟調に推移してきた株価ですが、先週あたりから上昇の勢いが強くなってきたように感じます。
米国の利上げに続いてEUの欧州中央銀行も利上げを表明しており、株式市場にとっては向かい風の状況です。
それでも株価は堅調に見えますね。
いったいこれは何が原因なのでしょうか?
本日のブログは株式市場に逆風が吹く中で、なぜ株価が上昇するのか理由を想定してみます。
米国の利上げについては「パウエルショック!米国ジャクソンホール会議で利上げ継続発表」も見てください。
欧州中央銀行(ECB)も0.75%の利上げを発表
欧州中央銀行(ECB)は9月8日に政策金利を0.75%引き上げる決定を行いました。
0.75%は米国の利上げ幅と同じですが、EUにとっては画期的な意味を持ちます。
実はEUが結成されて一度に0.75%の利上げを行うのは初めてで、通常の利上げの3倍になります。
つまり、それだけヨーロッパで物価上昇が進んでいることが分かりますね。
ECBのラガルド総裁はヨーロッパにおける供給問題に言及しており、とくにエネルギー不足については金融政策では解決できないことも示唆しています。
これはウクライナ紛争による天然ガスが問題になっているよね?
ラガルド総裁の発言をみると、「ヨーロッパのインフレ進行は天然ガスや原油などのエネルギー不足による価格高騰が要因」だと考えています。
つまりエネルギー価格が上昇することで、全体的な物価が上昇しているんだよ。
だから金融政策でインフレ率を2%に誘導したい考えなんだけど、「金融政策ではエネルギー不足を解消できない」のも事実だと話しています。
ECBは抜本的解決であるエネルギー不足は解決できないけど、金融政策でインフレを抑える対策は継続すると話しています。
ラガルド総裁の話を見ると、「エネルギー不足が解消できないけど利上げでインフレを抑え込む」と受け取れます。
でもこれは下手をするとヨーロッパ全体の景気を減速させる要因にもなります。
EUの成長率は2022年の3.1%から、2023年は0.9%まで下がる予想を出しており、EU内の格差も広がるように感じます。
EUでは問題の多くがウクライナ紛争に関係しているので、紛争が解消されれば先が見えてくると思うのですが…
米国FRBパウエル議長が利上げ継続を明言
米国FRBのパウエル議長が9月8日に「FRBがインフレの抑制に強くコミットしている」と発言し、9月のFOMCにおいても大幅な利上げを実施することを示唆しました。
利上げ幅はどの程度になるのかな?
ECBも同日に0.75%の利上げを実施したから、米国も意識した数字になるよね。
パウエル議長はインフレ抑制を「穏やかに進める(ソフトランディング)」と話していることから、いきなり1.0%を超える利上げはないと思いますね。
市場の予測もパウエル議長の発言を見て、アナリストによる「0.75%の利上げ予想」の確率が上昇しました。
また、別のFOMC委員も0.75%の利上げを支持するコメントをだしているので、9月20日から開催されるFOMCでは0.75%の利上げが実施される可能性は高いと思います。
0.75%の利上げ予想なのに株価が上昇するなぜ?

この流れから多くの米国アナリストは次回の利上げ予想を0.5%期待から、0.75%へ修正していますが、株価に対する影響は大きくありませんでした。
0.5%から0.75%に上がったのに株価に影響がなかったのはなぜ?
まず重要なポイントは、FRBが利上げによる経済の悪影響が限定的だと考えていることです。
ソフトランディングとは景気後退(リセッション)を起こさないで、インフレを抑制することなので、米国経済の成長は大きく落ち込まないことが予想されます。
FRBが無理なインフレ抑制ではなく、柔軟な政策を進める方針であることが好感されたようですね。
また米国の失業率や雇用も改善していることから、リセッションの不安が解消されたことも裏付けとしてあるようです。
米8月CPIも減速の予想が追風か?
米国の8月消費者物価指数(CPI)が9月13日に発表されますが、ガソリン価格の下落により先月に続き若干の改善が期待できます。
CPIが改善することは物価上昇が一段落していることを表していますが、ガソリンなどのエネルギー価格以外は引き続き高い水準で推移しているので、CPIだけでインフレ状況を判断するのは難しいかもしれません。
FRBはCPIの結果が改善されていても、0.75%の利上げを実施すると考えられており、8月のCPIの結果だけでは方針は変えないでしょう。
しかし、株式市場としてはCPIが改善することで、来年以降の利上げ速度が抑えられることから、CPIの予想は好感を持って受け取られているようです。
EUと米国の違いで状況が見える
EUでは利上げは抜本的な解決にならない金融対策だったけど、米国はそれとは違うの?
ドル・ユーロの為替を見てもわかるかど、ユーロも円と同じくユーロ安が進行してますね。
その理由がやっぱりエネルギーなんだよ。
ヨーロッパのエネルギーは原油以外に天然ガスが中心ですが、ウクライナ紛争によるロシアに対する経済制裁により天然ガスが高騰しています。
対して、米国は自国で一定のエネルギーを生産しているので、ロシアの天然ガスの影響はありません。
現状ではインフレが進行する米国ですが、ヨーロッパのようなエネルギー不足までにはならないと思われることから、ドルがユーロに対しても円に対しても強くなっているようです。
日本の株価の行方を予想?
9月12日の日本株式市場は346円高と大幅な上昇からスタートしていますが、この理由は先週末の米国の株式市場が堅調だったことがが要因です。
米国経済のリセッションは日本経済にも大きく影響するからね。
取り合えずFRBがインフレ抑制をソフトランディングできる自信が日本にも影響したと言えるのかな?
また先週のパウエル議長の発言タイミングで、円が142円まで下落したことも好感されたようですね。
どうも最近の日本株は米国株と為替によりコントロールされている印象を受けます。
しかし、日銀は現状では利上げの予定はなく、さらに輸出企業を中心に業績も拡大しているので、「株価が大きく下落する可能性は低いのではないか?」と個人的には予想しています。
まとめ
9月8日、EUの欧州中央銀行(ECB)がインフレ抑制を目的に政策金利を0.75%利上げしました。
同日、米国FRBパウエル議長は強いインフレ抑制策を継続すると発表しており、9月20日からのFOMCでは0.5%の期待値ではなく0.75%の利上げが実施されると見込まれています。
市場の期待は0.5%でしたが、0.75%利上げの観測が強まったようです。
さらに9月13日に発表される8月のCPIが改善されていても、0.75%の利上げは実施されると思います。
しかし、株式市場は失望よりもインフレの穏やかな解消見込みから大きな落ち込みは見られませんでした。
利上げ0.75%を米国市場が受け入れたことで、ドル高も一服しドル円も142円まで下落、9月12日の日経平均は300円程度の上昇となっています。
日本では日銀主導の金融緩和が継続される見通しなので、当分は利上げはないと思います。また輸出企業を中心とした好決算も期待できるので、株価が大きく崩れることは考えにくいのではないでしょうか?
※このブログはあくまでJ塾長の感想であり、投資を勧めるものではありません。投資は自己判断と責任でおこなってください。